2018年7月23日、県南医療圏・島原半島の地域中核病院であり、地域医療の向上のために貢献されている長崎県島原病院を訪れ、徳永能治院長、溝田小夜子副院長兼看護部長、フルタイム勤務で復職された呼吸器内科 菅崎七枝先生と、麻酔科 中島志帆先生の4名にお伺いしました。
●夫婦円満・家族の健康が仕事と子育てを両立するコツ 菅崎七枝先生インタビュー
●地元福岡から通う義母の献身的なサポートで仕事に集中 中島志帆先生インタビュー
人材流動性を高め、いかに新たな強みを見つけ出すか。
職員の多様性に備えてハード面を整備し、これからソフト面の強化に職員一丸となって取り組む長崎県島原病院

勤続年数7年で、12ヶ月の育児休業を取得し、2017年9月に復職された菅崎七枝先生に働き方と子育てについてお伺いしました。
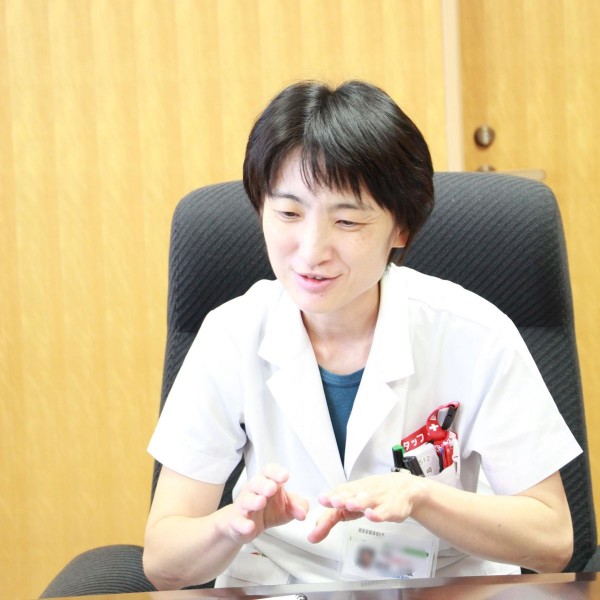
Q.現在の勤務形態はどのようになっていますか。
フルタイム勤務です。日当直は月約5回で、その間は夫が一人で子どもの面倒を見てくれています。夫は放射線技師なのですが、月4回程度待機があり、夜中でも呼び出しがあるので、お互い重ならないように調整しています。
入院患者を担当している時は、帰りが遅くなってしまうことが多かったですが、今は担当していないので、17時30分から18時の間には帰らせてもらっています。
Q.今の勤務形態で、デメリットに感じることはありますか。
家族には土日の日直や当直の時に負担をかけていると思います。あと、入院患者を担当していない分、病院にも迷惑をかけていると思っていますが、急な呼び出しがあった時に夫が不在の場合は対応できないので、病棟フリーにしてもらっていることはとてもありがたいです。いつか入院患者の主治医になりたいとは思っています。
Q.復帰した際の働き方はいかがでしたか。
復職した直後からフルタイム勤務でしたが、日当直は2か月くらい免除してもらいました。
Q.仕事と生活を両立するために工夫していることはありますか。
健康には気をつけています。親も子どもも元気でいれば、仕事に集中できます。あとは、夫婦仲良く協力し合うことですね。
Q.困っていることはありますか。
子どもの病気の時が一番困りますね。幸い元気な子で、これまで長い間保育園を休むことはなかったので助かっていますが、病気の時は夫婦で仕事を休める方が休んでいます。私が1〜2日休んだり、私と夫で午前と午後を交互に休んだりしながら対応しています。
Q.院内保育施設「たんぽぽ」を利用されているそうですが、いかがですか。
遅くまで延長もできますし、朝は8時から開園なのですが、早出があればその時に応じて預かってもらえます。少人数でかなり融通が効くので助かっていますね。
<溝田看護部長>
18時30分~20時まで延長保育ができます。さらに20時~22時は、事前予約で利用することができます。
Q.院内保育施設「たんぽぽ」を利用されているそうですが、いかがですか。
今後は専門医の資格を維持していきながら、できることをやっていきたいと思っています。特にがん薬物療法専門医を維持するためには5年毎の更新(書類申請と筆記試験)が必要です。資格を取るのも大変だったので、できれば維持したいですね。先週は臨床腫瘍学会に参加したのですが、初めて学会託児を利用しました。
Q.仕事と子育ての両立に苦慮している医師や若い医師へ、メッセージをお願いします。
施設毎にいろんな配慮をしてもらえるので、相談してみると希望の勤務形態に沿った働き方もできると思います。先輩の先生方もたくさんいると思うので、いろんな意見を聞いてみると良いかもしれません。
私自身は、同じ診療科にあまりロールモデルがいなかったのですが、看護師さんや薬剤師さんなどに相談にのってもらったり、中島志帆先生が私より先に復職を経験されて院内保育施設も利用されていたので、話を聞いたりしていました。
勤続年数5年で、研修医1年目に第1子妊娠、第2子は6ヶ月休業し、2016年4月に復職された中島志帆先生に働き方と子育てについてお伺いしました。

Q.現在の勤務形態はどのようになっていますか。
フルタイム勤務です。麻酔科は元々当直がないのですが、オンコールは免除してもらっています。回数は多くはないのですが、土日も呼ばれることがあるので、免除してもらいありがたいです。
できるだけ17時30分に帰りますが、手術が長引く時は終わるまでいます。
Q.現在の勤務形態はどのようになっていますか。
夫は当院の消化器内科で働いていますが、私より早く仕事が終わることは滅多にないので、なかなか分担は難しい状況です。保育園のお迎えは毎日義母にお願いしています。
夫の実家は福岡で、義母は日曜の夜に福岡から島原に来て、金曜の夜に福岡へ帰るという生活を送ってくれています。育児も家事も義母にサポートしてもらっているので、私は仕事に邁進できます。
Q. 今の勤務形態で、メリット・デメリットに感じることはありますか。
手術も最初から最後までみることができるし、術前・術後に患者さんを見に行くこともできているので、仕事の面ではすごく充実しています。
育児への関わりには賛否両論あるかとは思いますが、私としては今の状況がちょうど良いと思っています。土日は子どもたちと一緒に過ごしています。
Q. 今の勤務形態で、メリット・デメリットに感じることはありますか。
今、子どもが4歳と2歳で、研修中に1人目を出産して、研修が終わった時に2人目を出産しました。研修中に妊娠と出産をしたので研修は全部で3年かかりました。
病院にはご迷惑をおかけしてしまったと思いますが、当直免除など、配慮していただきました。
Q.今後のキャリアプランはどうお考えですか。
現在、標榜医を申請中です。認定医も今のところは取得できそうです。専門医を取得する際は、福岡の大学の医局に入局することになると思います。しかし専門医は、取得した後に維持していくのも難しいので、一旦保留にしようと思っています。
夫婦とも実家が福岡で、来年度は福岡に引っ越すので、週3日の非常勤でしばらく島原に通おうと思っています。
Q.仕事と子育ての両立に苦慮している医師や若い医師へ、メッセージをお願いします。
私は義母の全面サポートに助けられているという、おそらくかなり特殊な状況なので、あまり両立について言える立場ではないのですが、職場や上司の理解があってこそ、現状の働き方ができていると思っています。
もちろん育児も仕事も大事だし、妊娠・出産も早い方がいいとか遅い方がいいとか、考え方は人それぞれだと思います。私は、特に資格を持っていない状況で子どもを出産したので、今後のキャリアにも関わってくるとは思いますが、個人的には、授かりものだと思っています。
徳永能治院長に病院として両立支援の取り組みや考えなどについて伺いました。

Q.病院として育児・介護支援に関して取り組んでいることありますか。
2年前の2016年4月1日に「長崎県島原病院 院内保育施設たんぽぽ」を開設したことでしょうか。子育て中の医師の支援を行う一方で、部署内でどのように勤務体制を整えるか、両方の調整が必要です。
医師数が多ければ融通が利くかもしれませんが、子育て中の医師本人も言い出しにくいでしょうから、病院が調整役を務めなければいけません。
フォロー体制「案」を作成すること自体に無理がある、という現状で、それでも各部署で科長が根回しして、何とかできる事を生み出してくれているのが実態です。
保育所そのものの運営も病院としては不得手なため、外部委託をしています。外部委託でうまく運営できているのか、近隣の保育所と比較してアドバンテージ(強み・有利な点)がどれくらいあるのかなど、標準以上の設備や利用者の満足度を満たしているのか検証が必要だと考えています。
全てが小規模ですから、何かを支援するということは、残りの人達が色々工夫しないといけない、この作業を前向きに検討しなければいけないと感じています。
Q. ワークライフバランスを意識した経営戦略や経営上の効果はありますか。
院内保育施設運営に係る支出は年間一千数百万円くらいです。補助金等がありますので、その支出額が病院に痛手をもたらしていると思ったことはありません。むしろ、単に保育所という形であるだけで、高い機能を持ち合わせているわけではありませんので、行事等を含めてもう少しどうにか企画しないといけないのかなと思っています。
箱(建築物)を作れば良いという話ではなくて、近隣の保育施設は歴史的に古いところが多いようですが、親子参加型のイベントを行ったりして工夫を凝らしているようです。
当院でも園児が増えるように改善点の洗い出しを行い、対策を検討したいと思います。
(南副センター長)女性医師が院内保育施設を利用する一番のメリットは、0・1・2・3歳児が待機児童とならずに預け先が確保できるため、復職するタイミングを逃さない点だと思います。逆に4・5・6歳児の受入はナシにする、というやり方もあると思います。
Q.院長からメッセージをお願いします。
病院として、何か新しい運営をしようと検討する際は、当たり前のことですが常に職員全体への還元を意識しなければいけません。その中で、医師に限らず、病院は女性が主体となって働いているところですから、その人達が働きやすく、なおかつ将来に希望を持てるような病院にしないといけないと考えています。
いろいろな休みを取得できるか、例えば夫婦で勤めている場合は、お互いに休みをバランス良く取得できるかなどを含めて考えなければいけないと思っています。
今は職員募集をしても、なかなか人材が見つからない時代ですので、むしろ職員が減る中、足りない中での運用を、各部署内でどう上手く調整するかという意見を集める機会を作ろうと思います。
溝田小夜子看護部長に、看護部の育児・介護支援に関する取り組みをお伺いしました。

Q.看護部として、育児・介護支援などの取り組みを教えてください。
制度的には、全職員が同じ支援内容になります。看護師の育児休業取得期間の平均を調べたところ、昨年2017年度は12か月、2016年度は16か月でした。1年以上の取得者が多いです。各々に必要な育児休業を取得してもらって、復帰した時にしっかり働けるようにと思います。
また、地元出身で生活のベース(基盤)が島原にある職員がほとんどです。第2子、第3子を出産しながら働き続けており、当院では出産を機に退職するケースはほとんどありません。育児休業取得率も100%です。
Q.復職直後は、短時間勤務からのスタートですか。
短時間の育児休暇(育児のための早退)を2時間、子が3歳まで取得できる制度があります。現場の状況で必ず帰れるわけではありませんが、早めに帰って育児の時間に充てられます。
Q.夜勤の状況はいかがですか。
当院では、復職後から夜勤に入ってもらいますので、夜勤ができるようになってから復職されてきます。お子さんのお世話は、家族・夫婦間で調整しているようです。
3交代・2交代の病棟での復職は難しいという相談があった場合、手術室(オンコール)や外来は、夜勤が月3~4回程度なので、復帰しやすい部署へ調整することもあります。
Q.当直できる環境を整えてから復職されてくるので、夜勤は人手が足りていますか。
妊娠中は夜勤が免除されるので、調整に苦慮するところでもありますが、お互い様の状況で順番にという感じで何とかやっています。以前は病棟間の異動はなかったのですが、夜勤免除や育児休業取得者が病棟に偏ってしまう場合は、職員の負担を減らすために年度途中の配置換えなど行い、部署間の調整を図るようになりました。
Q.育児休業中の職員へ、看護部から定期的にフォローはされていますか。
部長の私からこまめに連絡を入れるとプレッシャーに感じてしまう面もあると思いますので、(各部署の)師長を通して情報収集をしてもらっています。
復帰時期を検討中との情報が入れば、私が直接確認することもあります。復職時の配属先は、基本的には育児休業に入る直前まで勤務していた部署、という取り決めです。その方が周囲のスタッフとの連携も取りやすいためです。
Q.看護師部長からのメッセージをお願いします。
育児休業を取得するその期間は、各職員の人生の中で大切な時期だと思って、お互いが支援できる環境づくりを心がけています。
育児中は、自分のキャリアに関する研修がなかなか進まないというジレンマもあると思いますが、その時にしかできないことを、バランスを取りながらやることが大切だと思います。人材育成は、段階的に長い目でみて考えていきたいと思います。
―貴重なお話をありがとうございました。
院内保育所を見学させていただきました。

2016年4月に病院の敷地内に新築し、駐車場も完備されていて利便性に優れています。
1階が「たんぽぽ保育所」、2階は研修医や看護師のための宿舎として1DK(家電付き)が4部屋用意されています。

定員数:30名、広さ:約200㎡、開園時間:8時~18時30分(最長22時まで延長あり)
現在5名(医師2名・薬剤師1名・療法士1名・診療放射線技師1名)の職員のお子さんが利用中です。学童の受け入れも行うなど、柔軟に対応されていました。
職員は地元出身者が多いため、子育て中の職員は、仕事と生活の両立を図るために「近居」(親世帯と子世帯が気軽に行き来できる範囲でそれぞれ別の家に居住すること)して支え合うケースが多いとのことです。



院内保育所の利用感想をお二人の女性医師へお伺いしました。
【中島先生】
開設当初は、うちの子2人だけの利用でしたが、途中十数名まで増えました。乳児を預けるには適した環境で、とても助かっていました。しかし、行事が少なく、運動会やお遊戯会などを経験させたくて、幼稚園へ転園しました。
【南副センター長】
0・1・2・3歳児の頃を病院内で預かってもらえれば、十分助かりますよね。
【菅崎先生】
現在1歳の子どもを預けていて、幼稚園入園頃まで利用しようと思っています。少人数で融通が利き、よくみてもらってすごく助かっています。
<副センター長の感想>
お2人の子育て中の女性医師は、どちらも、長崎県島原病院で産休や育休をとり、院内保育園を利用されて復職されており、先生方をとりまく環境がとても良いのだと感じました。
徳永院長は、院内保育施設の充実にも心配りされておりますが、「病児」保育施設がなく、「病後児」保育施設のみがある島原半島において、子どもが病気の時に休めない場合のサポートも、今後検討してほしいと思います。
専門医としての使命感をもって夫婦仲良く両立を頑張っている菅崎先生、親族のサポートを得て仕事に集中できる中島先生、どちらも島原の医療にしっかり貢献されており、また看護部では、復職後は夜勤免除のない体制が構築されており、子どもがいても、しっかり働くという姿勢を感じました。

